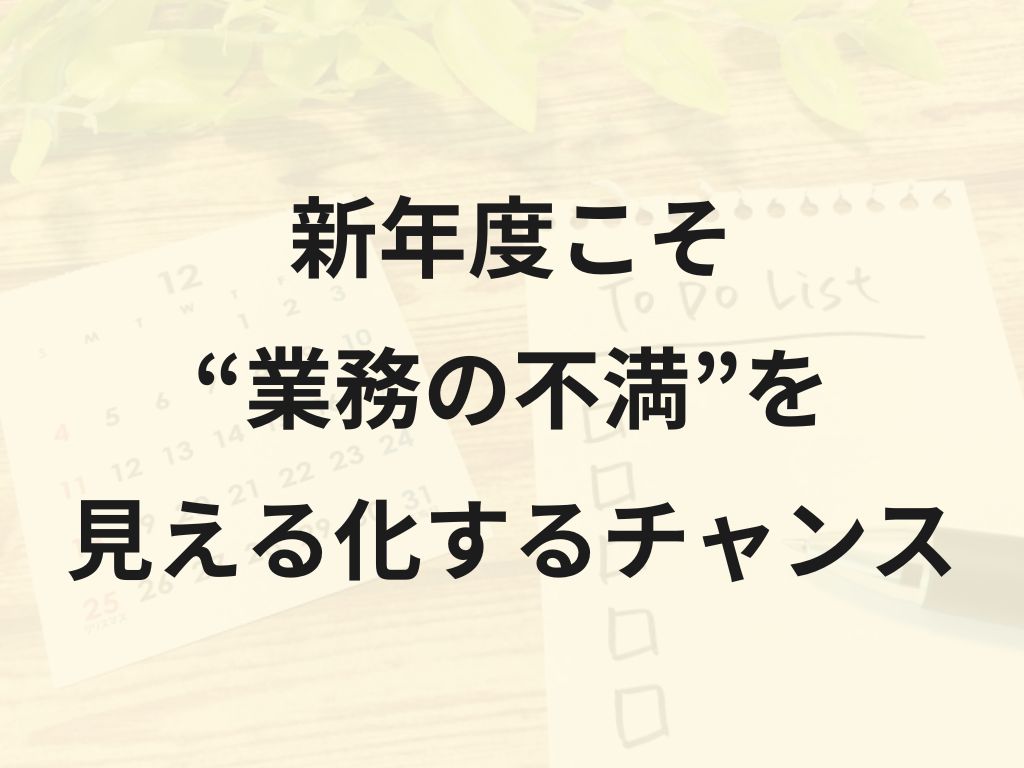

新年度が始まると、会社の仕事は一気に増えます。
新しい目標の設定、異動や引き継ぎ、繁忙期の準備…。
そんな中、「人手が足りない」「仕事が回らない」といった声が社内で聞こえ始めることはありませんか?
気づけば、一部の従業員に負担が偏り、疲れや不満がたまってしまう。
最悪の場合、それが原因で大事なスタッフが辞めてしまうこともあります。
特に、もともと人手が少ない会社では、新しい人を採用するのも簡単ではありません。
その結果、限られた人数で何とか仕事を回そうとするうちに、長時間労働が当たり前になったり、モチベーションが下がったり…。
そうなる前に、今こそ「業務の見直し」をしてみませんか?
本記事では、業務を上手に分担し、限られた人数でも効率よく働ける仕組みをつくるための方法をわかりやすく解説します。
新年度を機に従業員の不満を減らし、会社全体のパフォーマンスを上げるためのヒントを、ぜひチェックしてみてください!
目次
1. 人手不足が引き起こす“負の連鎖”とは?
人手が足りない状態が続くと、仕事が一部の従業員に集中し、組織全体のバランスが崩れます。
その結果、以下のような3つの大きな問題が発生し、最終的には企業の成長を妨げる原因となります。
| 問題点 | 考えられるリスク |
|---|---|
| 業務負担の偏り | 長時間労働、離職、モチベーション低下 |
| 属人化の進行 | 業務のブラックボックス化、引き継ぎ困難 |
| 生産性の低下 | 組織全体の業績悪化、競争力低下 |
①限界ギリギリ…業務の偏りが従業員を疲弊させる
人手不足の企業では、一人ひとりの仕事量が増えがちです。
特に、経験のあるスタッフに業務が集中し、「これ以上は無理だ」と感じる状況が生まれやすくなります。
長時間労働が常態化し、休みを取りづらくなることで、心身の疲労が蓄積。
最悪の場合、従業員が離職し、さらに人手不足が深刻化する“負のスパイラル”に陥ります。
②その仕事、あの人だけ?属人化がもたらす落とし穴
特定の従業員にしかできない仕事が増えると、業務が“属人化”してしまいます。
例えば、「Aさんしかできない作業」がある場合、そのAさんが突然休んだり退職したりすると、仕事がストップしてしまいます。
また、新しい従業員が入っても業務の全体像が見えづらく、引き継ぎがスムーズにいかないという問題も発生します。
③モチベーション低下→業績悪化…負の連鎖に
業務負担の偏りや属人化が進むと、従業員のモチベーションが下がり、作業効率も低下します。
そうなると、残業が増えたり、納期が遅れたりといった問題が発生し、企業全体の生産性が落ちてしまいます。
最終的には、競争力の低下や業績の悪化につながり、会社としての成長が止まってしまう可能性もあります。
解決策:業務の「可視化」と「再分配」がカギ
このような負の連鎖を断ち切るには、まず業務の全体像を「可視化」し、適切に「再分配」することが重要です。
誰が、どの業務を、どれくらいの負担で行っているのかを整理することで、偏りを防ぎ、組織全体で業務をスムーズに回せる仕組みを作ることができます。
次の章では、人員が少なくても効率的に業務を進めるための「業務棚卸」の方法を詳しく解説していきます。
2. 小さな組織こそ見直したい、業務棚卸の基本ステップ
仕事の進め方を見直すためには、まず「今どんな業務が、誰に、どれだけの量で割り当てられているのか」をしっかり把握することが大切です。
これが、いわゆる「業務棚卸(たなおろし)」の第一歩です。
ここでは、限られた人数でも取り組めるシンプルな3ステップをご紹介します。
① まずは全部見える化!“どんな業務があるか”を洗い出そう
まずやるべきは、「どんな仕事を誰がどのくらいやっているのか」を書き出すことです。
たとえば介護の現場では、「利用者の移乗を手伝う」「送迎する」「おむつ交換をする」といった業務がありますが、これらを一つずつ細かく分けて、時間や頻度、担当者などを一覧にしていきます。
| 業務内容 | 所要時間 | 担当者 | 頻度 |
|---|---|---|---|
| 移乗介助 | 約15分 | Aさん | 1日3回 |
| 送迎 | 約30分 | Bさん | 週2回 |
| おむつ交換 | 約5分 | Cさん | 1日5回 |
このようにリストにすることで、「誰に仕事が偏っているのか」「時間がかかりすぎている業務はどれか」が一目でわかります。
※今回は介護の現場を例にしていますが、事務作業や営業、清掃、メール対応など、どの職種でも同じように可視化が可能です。
② 優先順位がカギ!“今やるべき業務”を見極める
次に、「すぐに対応が必要な業務(緊急度)」と「会社の目標にどれだけ関係があるか(重要度)」の2つの観点で分類してみましょう。
たとえば、「お客様対応」は緊急かつ重要ですが、「書類の整理」は緊急ではないけれど重要な業務かもしれません。
このように整理することで、限られた時間と人手の中で、何を優先し何に力を入れるべきかがはっきりします。
③ “その作業、人がやる必要ある?”自動化・外注のススメ
本当に自分たちでやるべき仕事はどれか?と考えることも大切です。
たとえば、毎月決まった作業だけの経理業務や、決まった内容の資料作成などは、外部に任せたり、RPA(ロボットによる自動化)ツールを導入することで、大幅に時間を短縮できます。
最近では、よくある問い合わせへの自動応答(チャットボット)や、経費精算・勤怠管理といった事務処理の自動化が進んでいます。
これと同じように、他の仕事でも「誰かがやらなきゃ」から「どうすれば省力化できるか」に視点を変えることで、全体の業務負担を減らすことができます。
💡ポイント💡現場を整えるカギは「今の業務を知ること」
「何が、誰に、どのくらいの負担になっているのか」を正しく把握することで、無理なく仕事を分け合える仕組みを作ることができます。
このステップを飛ばしてしまうと、改善の打ち手が的外れになってしまうこともあるため、丁寧に取り組むことが大切です。
3. 業務を上手に分担して、少ない人数でもしっかり回る仕組みを作ろう
業務の見える化と優先順位づけが終わったら、次は「誰に、どんな仕事を任せるか」を考える段階です。
人手が少ないからこそ、仕事の割り振り方がとても重要になります。
ただ「なんとなくできそうな人に任せる」のではなく、会社全体で仕事がうまく回るように工夫することが、従業員の不満を減らし、組織のパフォーマンスを上げるカギになります。
ここでは、効果的な業務分担を実現するための4つの工夫をご紹介します。
① 一人で抱え込まない!多能工化でチームの柔軟性を高める
誰かにしかできない仕事が多いと、その人が休んだときに業務が止まってしまいます。
そこで有効なのが「多能工化」。
一人がいくつかの仕事をこなせるように、日頃から少しずつ練習や引き継ぎをしておくことで、急な欠員にも柔軟に対応できる組織になります。
ポイントは、「全部を完璧にこなせるようにする」のではなく、「ある程度対応できる人を増やす」ことです。
これだけでチーム全体の安心感がぐっと高まるでしょう。
② 属人化を解消する鍵は“見える化と仕組み化”
たとえば「この作業はAさんじゃないとできない」といった属人化が起きている場合、仕事のやり方が明文化されていない可能性があります。
業務ごとにマニュアルを作ったり、作業手順を整理したりして「誰がやっても同じ結果になる」ようにすれば、仕事の引き継ぎがスムーズになり、ミスも減ります。
さらに、無駄な手順を見直してシンプルにすることで、作業時間の短縮にもつながりますね。
③ ツールを味方に!業務効率化は“仕組み選び”が9割
現代の業務では、便利なツールを上手に使うことも大きなポイントです。
たとえば:
・チャットツール(例:LINE WORKS、Slack、Chatwork)でやりとりの効率化やタスク管理
・定型業務はRPA(ロボットによる自動化)で省力化
など、ITツールを取り入れることで、人に頼らなくても「仕事が回る仕組み」をつくることができます。
④ コア業務に集中するための“手放し戦略”
「何でも社内でやろう」とすると、限られた人材に負担が集中してしまいます。
たとえば、経理や給与計算、採用業務、IT管理など、専門知識が必要で時間もかかる業務は、外部に任せることも選択肢のひとつです。
全部外注する必要はありませんが、「これは外に出した方が早くて正確」と思える業務があれば、思い切って委託することで、社内で本来集中すべき仕事にエネルギーを使えるようになります。
特に新年度は、役割の見直しや業務分担を見直すチャンスです。「不満がたまりにくい」「仕事がまわる」組織を目指して、できることから始めてみましょう。
4. 業務分担を変えるときに気をつけたい3つのポイント
業務の見える化ができて、「よし、分担を見直そう!」となったときに、忘れてはいけないのが“人の気持ち”への配慮です。
業務分担を変えることは、スタッフにとって大きな変化。
「急に仕事が変わるなんて不安…」「なんで私が?」と感じてしまう人もいるかもしれません。
せっかく良い仕組みをつくっても、従業員本人が納得していなければうまくいきません。
ここでは、業務分担をスムーズに進めるために大切な3つのポイントを紹介します。
| 注意点 | 詳細 |
|---|---|
| 変更内容の明確な説明と合意形成 | なぜ業務を見直すのか、どんな変化があるのかをしっかり説明し、従業員の理解と納得を得る。 |
| 従業員の不安への配慮とサポート | 不安や疑問に丁寧に対応し、研修やOJTなどのサポートで安心感を持たせる。 |
| 試行期間とフィードバックの活用 | いきなり完全に変えるのではなく、試しながら改善していく柔軟な姿勢が大切。 |
① 変更には理由を。納得を生む分担変更の伝え方
業務分担の変更にあたってまず大切なのは、「なぜ今、分担を見直すのか」を従業員にわかりやすく説明することです。
たとえば、
・「○○さんの負担が増えていて、このままだと体調を崩してしまうかもしれない」
・「業務の偏りをなくして、全員が安心して働けるようにしたい」
といった目的をきちんと伝えることで、彼らも納得しやすくなります。
説明の場では、一方的に伝えるのではなく、「意見を聞く姿勢」も大切にしましょう。ちょっとした疑問や不安を聞いてもらえるだけで、受け入れやすさが変わってきます。
② 不安を安心に変える!サポートと声かけの工夫
新しい業務を任されることに、誰しも少なからず不安を感じます。
その不安を放っておくと、「なぜ自分ばかり…」と不満につながりかねません。
そこで効果的なのが、
・実際に仕事を覚えるためのOJT(現場での実地指導)
・わかりやすい業務マニュアル
・相談できるサポート体制
など、安心してスタートできる環境づくりです。
「やってみようかな」と思えるような後押しをすることで、前向きな変化が起こりやすくなります。
③ 完璧より“試しながら”が成功のコツ
業務分担の見直しは、一度決めたら終わり…ではありません。
実際にやってみると、「思ったより大変だった」「この分担の方がよかったかも」といった声が出てくることもあります。
だからこそ、まずは「お試し期間」として運用し、スタッフからのフィードバックを取り入れながら調整していく姿勢が重要です。
「完璧に整えてからスタート」ではなく、動かしながら整えていく柔軟さが、組織にフィットした働き方をつくるカギになります。
💡ポイント💡人も業務も“動きながら整える”
業務の分担を変えるときには、仕組みだけでなく“人の気持ち”も大切にしましょう。
説明 → サポート → 試行 → 調整 という流れを意識することで、従業員の不安や不満を減らしながら、スムーズに業務を最適化していくことができます。
5. 分担の見直しが定着に効く3つの理由
「業務の見える化」や「分担の工夫」、「変更時の注意点」などを押さえて、実際に業務分担を見直してみると、会社にも従業員にもたくさんの“いい変化”が生まれます。
単に「仕事が回るようになる」だけでなく、働く人の気持ちやチームの力、会社の成長にもつながる大きなメリットがあるのです。
ここでは、業務分担の見直しで得られる3つの代表的なメリットをご紹介します。
| メリット | 内容 |
|---|---|
| 従業員満足度の向上と離職率の低下 | 仕事の偏りがなくなり、無理なく働けるようになることで不満が減り、働きやすさがアップ。結果的に従業員が辞めにくくなる。 |
| 生産性の向上と業績の改善 | 誰にでも仕事ができる仕組みを整えることで、作業のムリ・ムダ・ムラが減り、仕事の質とスピードがアップ。 |
| 属人化の解消と組織力の強化 | 特定の人に頼らない体制をつくることで、チーム全体の力が底上げされ、ピンチにも強い会社になる。 |
① 働きやすさが定着につながる
業務の偏りがなくなり、「自分ばかり大変」という不満が減れば、従業員は安心して働けます。
また、それぞれのスキルや得意分野に合わせて業務を割り当てることで、「自分の力が活かされている」という実感も生まれ、やる気や自己成長にもつながります。
このように働きやすい環境が整えば、自然と離職率も下がっていきます。
② ムダを減らせば成果はもっと出る
業務を標準化したり、効率化ツールを導入したりすることで、作業のスピードや正確さが上がります。
特定の人だけに頼るのではなく、誰でもできる体制を整えることで、「待ち時間」や「手戻り」が減り、仕事全体の流れがスムーズになります。
次第に生産性が向上し、結果として企業の業績アップにもつながっていきます。
③ 支え合えるチームは強い
業務のやり方を共有・標準化することで、担当者が突然いなくなっても、他のメンバーが代わりに対応できるようになります。
これは、チーム全体の“対応力”が上がるということ。
さらに、業務内容が共有されることで、「こうすればもっと効率がいいんじゃない?」という改善アイデアも生まれやすくなり、会社全体の成長にもつながります。
💡ポイント💡分担の見直しが組織を育てる
働く人の不満を減らし、やる気を引き出し、チーム力を高める…そんな“土台”をつくる、とても大切な取り組みです。
このメリットを実感するためにも、まずはできることから少しずつ始めてみましょう。
まとめ:少ない人数でも成果が出せるチームにするために
新年度のスタートは、会社の中で起きている“ちょっとした違和感”に気づきやすいタイミングです。
たとえば、「あの人だけいつも残業している」「最近、○○さんの元気がない」――こうした小さなサインが、実は業務分担の偏りや、働く人の不満につながっているかもしれません。
とくに人手が限られている会社では、一人ひとりの働き方が会社全体に大きな影響を与えます。
だからこそ、業務の棚卸しと分担の見直しは、組織の“体調チェック”のようなもの。
早めに気づき、整えることで、従業員の不満や離職を防ぎ、持続可能な職場をつくることができます。
「何から始めたらいいかわからない」という方は、以下の5つをチェックしてみましょう:
| チェックポイント | 内容 |
|---|---|
| ✔業務量の見える化 | 誰が何をどれだけやっているかを整理し、負担の偏りを確認する |
| ✔スキルや経験の把握 | スタッフ一人ひとりの得意なことや現在の状態を理解する |
| ✔業務の標準化・簡素化 | 手順を整え、誰でもできるようにする |
| ✔ツールの活用 | 自動化・効率化のためにITツールを導入する |
| ✔外部委託の検討 | 社内で抱えなくてもよい業務は外部に任せる選択肢を持つ |
仕事のやり方を少し変えるだけで、従業員の気持ちが軽くなったり、チームの動きがスムーズになったりします。
「人が足りないから仕方ない」とあきらめず、できることから少しずつ。
それが、これからの時代に必要な“強くてしなやかな組織”づくりにつながっていきます。
“辞めない組織”をつくるヒント、もっと知りたくありませんか?

「業務の分担、これで本当に大丈夫?」「体制のゆがみが不満や離職につながっていない?」
定着の樹では、そんな不安や気づきを“放置しない”ための、組織体制や仕組みづくりの見直しに役立つヒントを毎月お届けしています。
📩 会員登録(無料)でできること:
・新着記事や専門家コラムをメールでまとめてご案内
・定着につながるセミナー・イベントへの優先案内
・メンバー限定の資料やコンテンツ記事が閲覧&ダウンロード可能
登録は30秒で完了&完全無料!
▼こちらから、今すぐご登録いただけます。
“人が辞めない組織づくり”を、一緒に始めてみませんか?




