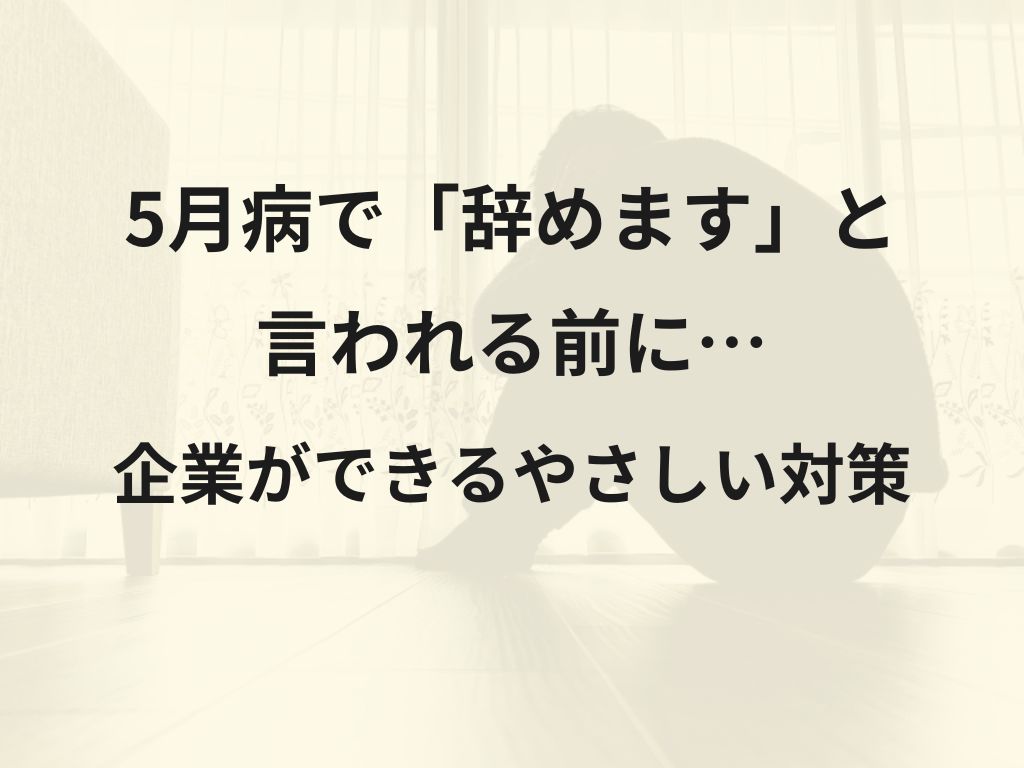
2025.04.28
5月病で「辞めます」と言われる前に…企業ができるやさしい対策

ゴールデンウィーク明け、職場の空気がどこか重たく感じることはありませんか?
新年度から1ヶ月が経過し、新入社員をはじめとした多くの従業員が、緊張と疲労を抱えながら5月を迎えます。
この時期に多く見られるのが、いわゆる「5月病」と呼ばれる心身の不調です。
企業にとっても、5月病への対策は従業員の定着や生産性に直結する重要な課題といえるでしょう。

はっしー
私も長期休暇明け近くなると『仕事するのめんどくさーい!』ってなります(泣)
なんとかなりませんかね?
この記事では、「5月病とは何か?」という基本から、企業の皆さんにぜひ休み明けに試してほしい対策まで、分かりやすく紹介していきます。
目次
1. 5月病とは?企業にとってのリスクとは?
5月病とは、ゴールデンウィーク明けに現れる心身の不調を総称する俗称です。
正式な医学用語ではありませんが、新しい環境への適応ストレスや長期休暇中の生活リズムの乱れなどが原因とされています。
特に新入社員や異動者など、環境の変化を経験した人ほど影響を受けやすくなります。
主な症状
- モチベーションの低下
- 倦怠感
- 集中力の欠如
- 不安感や憂うつ感
- 頭痛、消化器不良、睡眠障害など身体的不調
放置すれば、適応障害やうつ病に発展する可能性もあり、企業にとっては業務効率の低下や離職リスク増大といった深刻な影響を及ぼします。

はっしー
分かります…私もなんか、うっすら体調悪いです…休みたい…
2. ゴールデンウィーク明けに不調が出やすい理由
5月病が発生しやすいのは、長期休暇明けというタイミングが大きく影響しています。
休暇中に生活リズムが崩れたり、仕事から離れて気持ちが緩んだことで、再び仕事モードに切り替えるのが難しくなるのです。

はっしー
夜更かしして昼まで寝ちゃうと、戻すの大変なんですよね…
さらに、4月からの新生活に適応しようと頑張ってきた従業員ほど、5月に入って一気に疲れが出やすくなります。
ゴールデンウィークを「節目」として、緊張の糸が切れてしまうのです。
3. 企業が注目すべき5月病の兆候とは
5月病は誰にでも起こりうる一時的な不調です。
しかし、早期に兆候を察知し、対応できるかどうかで、その後の深刻化を防ぐことができます。
こんなサインはありませんか?
- 仕事への意欲が見られない
- 遅刻や欠勤が増えている
- コミュニケーションを避けるようになった
- 表情が暗く、覇気がない
- 身体の不調を頻繁に訴える

はっしー
“最近ちょっと元気ないな〜”って思ったら、さりげなく声をかけてもらえるとありがたいです…!
特に新入社員や異動者など、職場に慣れていないメンバーには注意を払いましょう。
本人も「自分が5月病かもしれない」と気づいていないこともあります。
4. 企業が取り組むべき5月病対策10選
企業としてできる5月病対策には、予防・早期発見・回復支援の視点で考えるといいでしょう。
以下に、すぐに取り組める具体的な対策を紹介します。
(1) 休暇前の準備支援
・休暇前に「仕事復帰の心構え」を共有し、不安を減らす。
・ゴールデンウィーク明けの業務スケジュールを可視化。

はっしー
休みが楽しみすぎて、復帰のことまで考えたくないんですけど…
でも事前に少し準備できると心が楽になりますよね!
(2) 復帰初日の配慮
・簡単な業務から始めるなど、無理のない立ち上がりを。

はっしー
初日からフルスロットルだと本当にきついです…
“ウォーミングアップ日”みたいな扱いにしてほしい!
(3) 雑談・ランチでの交流促進
・休暇中の出来事を共有できる場を設け、心理的な距離を縮める。

はっしー
ランチ会で“お休み何してた?”って話せるだけでも気持ちが和みますよね〜
(4) 柔軟な労働時間管理
・フレックス制やリモートワーク活用など、無理のない働き方を支援。

はっしー
出社が億劫な朝、在宅って選択肢があるだけで心の負担が全然違うんですよね…
(5) こまめな休暇取得の推奨
・週末に加えて「プレミアムフライデー」や週の中日に早上がりさせる習慣を設ける。

はっしー
小休止ってほんと大事!こまめに休める職場って信頼できます!
(6) メンター制度の導入
・新入社員や若手に寄り添う仕組みを整備。

はっしー
“困った時に話せる先輩”がいるだけで、安心感ぜんっぜん違いますよね
(7) ストレスマネジメント研修の実施
・自分の不調に気づき、セルフケアできる力を育てる。

はっしー
『なんか調子悪い』の正体を知れるって、それだけで救われることあると思います!
(8) キャリア支援の機会提供
・将来への不安を軽減し、仕事の意味づけをサポート。

はっしー
“この先どうなるんだろう…”っていうモヤモヤ、言葉にできる場があるとホッとします!
(9) 外部相談窓口の案内
・産業医やEAP(従業員支援プログラム)など、専門家への相談ルートを確保。

はっしー
社内で話しにくいことってありますもんね。第三者がいるって本当にありがたい。
(10) 全社的な理解促進と風土づくり
・管理職向け研修や社内報などで「5月病対策は企業の責任」と浸透させる。

はっしー
“気合いが足りない”って言われなくて済む職場、大事です!
まとめ:この記事のポイントをおさらい!
5月病は、新年度の疲れや長期休暇明けのギャップが原因で起こりやすい、誰にでも起こりうる心身の不調です。
企業が対策を怠れば、業務効率の低下や離職リスクに直結する重大な課題になります。
今回ご紹介した、企業が実施できる対策は以下の10点でした:
- 休暇前の準備支援
- 復帰初日の配慮
- 雑談・ランチでの交流促進
- 柔軟な労働時間管理
- こまめな休暇取得の推奨
- メンター制度の導入
- ストレスマネジメント研修の実施
- キャリア支援の機会提供
- 外部相談窓口の案内
- 全社的な理解促進と風土づくり

はっしー
こうして見ると、ほんのちょっとの工夫で救われる人って多い気がします…
“人ごと”じゃなくて“みんなごと”として考えたいですよね!
企業にとって大切なのは、“不調にならないための予防”と“早めの声かけ・対応”。
職場全体で心地よく働ける環境を整えていくことが、従業員の健康と意欲を支え、企業の成長にもつながりますよ。
離職者を増やさないちょっとした工夫を知りたいなら

「長期休み明けも従業員みんながスムーズに立ち上がるにはどうすればいい?」
「いい雰囲気の職場づくりって?」
この記事を読んでそんな疑問を持った方は、ぜひ『定着の樹』の会員登録をご検討ください。
定着の樹では、
- 各分野専門家による監修記事
- 採用・定着の工夫 など、経営者や人事担当者に役立つ情報をお届け
- 月1回のメールマガジンで最新記事やイベント情報もお知らせしています。
登録は30秒で完了&完全無料!
▼こちらから、今すぐご登録いただけます。



