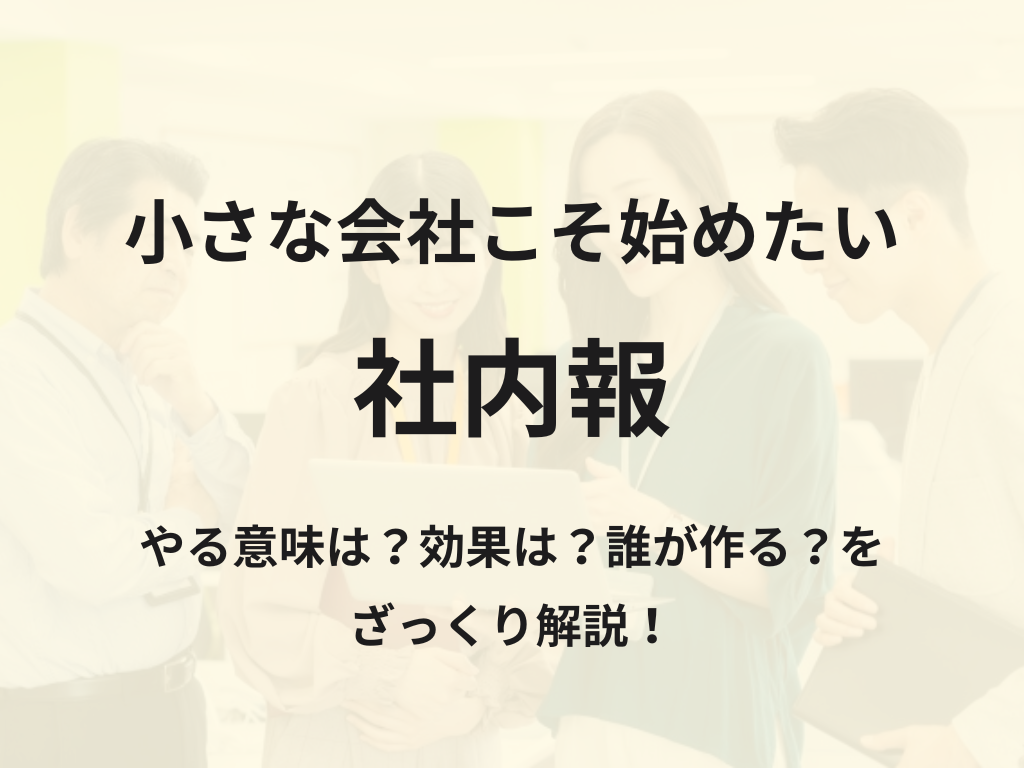
10月5日は「社内報の日」。
「社内を統合する」という言葉から、語呂合わせの「とう(10)ご(5)う=統合」にちなんで制定された記念日だそうです。
社内報は経営方針や事業の進捗を共有するだけでなく、従業員同士のつながりを強め、会社の文化を形づくる大切なツールといえます。
近年では、社員の定着やモチベーション向上を目的に社内報を導入する企業が増えているようです。
紙の冊子やPDF、Web社内報など形式はさまざまですが、共通しているのは「会社と社員をつなぐ」役割です。
本記事では、社内報の意味や効果、導入の基本についてご紹介します。
みなさんの職場でも社内報を上手に活用することで、働きやすい環境づくりや離職防止につなげられるかもしれません。
1. 社内報とは?基本と目的
1-1. 社内報の定義
社内報とは、従業員に向けて会社の情報や活動を発信する社内コミュニケーションツールです。
紙の冊子やデジタル配信、Webサイトなど媒体はさまざまですが、共通しているのは「会社と社員をつなぐ」役割を担うこととされています。
1-2. 社内報を出す目的と具体例
社内報はネタ次第で以下の5つのような効果をもたらします。
① 経営方針や事業状況の共有
社員が経営層の考えや会社の方向性を理解することで、安心感と納得感を持って働ける。
ネタ例:
・社長インタビューで「今年度の経営方針」や「中期計画」をわかりやすく解説
・新規プロジェクトの進捗レポートを紹介 など
② 従業員エンゲージメントの向上
一緒に働く仲間の人となりを知ることで一体感や誇りが生まれ、社員のモチベーションが高まる。
ネタ例:
・今月の活躍社員紹介/社内アワード受賞者インタビュー
・現場スタッフの工夫や改善事例を特集 など
③ 企業文化・理念の根付かせる
抽象的な理念を具体的な行動に落とし込み、繰り返し発信することで組織文化が根付く。
ネタ例:
・企業理念を実務の場面で実践している社員のエピソード紹介
・会社の歴史や創業者の思いを特集するページ など
④ コミュニケーション活性化
普段接点が少ない部署や職種への理解を深め、横のつながりを強化する。
ネタ例:
・「他部署の仕事を知ろう」企画
・クロスインタビュー形式で部署間の協働事例を紹介 など
⑤ 定着率アップ
従業員が「自分は大切にされている」と感じる体験をすることで、この会社でキャリアを続けたいと思える。
ネタ例:
・福利厚生の活用体験談
・育休から復帰した社員の声
・キャリアステップの紹介 など
これらの目的を備えた社内報こそが、社員にとって「読む価値がある」と感じられるツールになり、組織の力を強めることにつながります。
2. 社内報を出す意味と効果
社内報は単なる情報誌ではなく、職場の課題を解決するための有効なツールにもなります。
現場で起こりやすい問題と、その解決策を見てみましょう。
① 「聞いてない!」を減らす
問題の場面:制度変更や方針が伝わらず、「初耳です」と不満が出る。
解決策:社内報で背景や決定事項を整理して共有。
期待される効果:全社員が同じタイミングで情報を得られ、公平感と信頼感が高まる。
② 支店やリモートの孤立感をなくす
問題の場面:拠点や在宅社員が「会社から切り離されている」と感じる。
解決策:各拠点の取り組みや社員インタビューを紹介。
期待される効果:「自分も組織の一員だ」と実感でき、定着率向上に直結。
③ 成功例や工夫を全社で共有できる
問題の場面:現場の改善事例や成功例が他部署に届かない。
解決策:取り組みを記事にして横展開できる形で共有。
期待される効果:学びの循環が生まれ、前向きなチャレンジ意欲も高まる。
④ 会社の雰囲気を外にも伝えられる
問題の場面:採用活動で「社風が見えない」とミスマッチが発生。
解決策:社内報の一部を外部公開し、社員の姿を伝える。
期待される効果:応募者が安心して入社を決められ、早期離職防止につながる。
⑤ 制度を「知らなかった」で終わらせない
問題の場面:福利厚生や制度が浸透せず、利用されない。
解決策:社内報で制度紹介や利用者の声を掲載。
期待される効果:活用が進み、社員の満足度や働きやすさが高まる。
このような場面で社内報を活用することで、従業員が安心して働ける職場づくりへと近づいていきます。
3. 社内報の媒体と特徴
社内報を導入する際は、自社に合った媒体を選ぶことが大切です。
代表的な形式と特徴を整理します。
| 媒体 | メリット | デメリット | 向いている企業 |
|---|---|---|---|
| 紙媒体 (冊子・チラシ) | ・手に取りやすい ・保存されやすい ・現場や店舗でも配布可能 | ・印刷・配送コストが高い ・更新に時間がかかる | 製造業や店舗など、デジタル環境が整っていない職場 |
| PDF配布 (メール・社内システム) | ・低コスト ・簡単に配布できる ・内製化しやすい | ・印刷しないと読まれにくい ・埋もれて見落とされることも | 中小企業や「まずは手軽に始めたい」会社 |
| Web社内報 (イントラ・社内ポータル) | ・更新が容易 ・動画やリンクも活用可能 ・検索性が高い | ・導入・運用コストがかかる ・システム整備が必要 | ITリテラシーが高い組織、 社員数の多い会社 |
| 社内SNS・チャットツール (Slack/Teamsなど) | ・リアルタイム性が高い ・コメントや双方向のやりとりが可能 | ・情報が流れやすく、読み返しに不向き ・情報整理が必要 | フラットな文化のある職場、 スピード重視の企業 |
| ハイブリッド型 (複数併用) | ・速報と深掘り記事を使い分けられる ・読者に合わせた届け方が可能 | ・運用ルールを整えないと混乱しやすい ・リソースが分散 | 「ニュースはチャット、特集は冊子」など両立させたい企業 |
3-1. 社内報の媒体を選ぶ際のチェックポイント
社内報の媒体は「流行っているから」や「手軽だから」だけで選ぶと失敗しがちです。
自社の状況に合わせて検討することが大切です。
✔ 社員数と年齢層
社員数が多い場合はWeb社内報のほうが管理しやすく、検索性も高まります。
一方、シニア層の多い職場では紙のほうが確実に届くことも。
✔ 職場のIT環境
PCやスマホを日常的に使うかどうかで選択肢は変わります。
現場作業が中心で端末利用が少ないなら紙、オフィスワーク中心ならデジタル媒体が適しています。
✔ 予算とリソース
印刷やシステム構築はコストがかかります。
低コストで始めたいならPDF配布や簡易Web、外部委託するなら長期的な費用対効果も検討が必要です。
✔ 情報の内容と発信スピード
速報性が求められる内容(人事異動やイベント告知)はチャットツールと相性が良く、方針説明や特集記事は紙やWeb社内報の方がじっくり伝えられます。
✔ 社内文化や雰囲気
「きちんと残る形で読みたい」文化がある会社と、
「気軽にコメントして盛り上がりたい」会社とでは、適した媒体が変わります。
こうした観点を踏まえて、自社に合った媒体を選ぶことが、社内報を定着させる第一歩になります。
4. 誰が作る?社内報の制作体制
4-1. 中小企業では「総務・広報・人事」が一手に担うことが多い
大企業のように編集長や委員会を設けるのは理想ですが、従業員数の少ない中小企業では難しいのが現実です。
実際には、総務や広報、人事が企画から原稿作成、レイアウト調整、配布までをまとめて担当するケースが一般的です。
小さな体制でも無理なく続けられることが、社内報の運用を成功させる第一歩です。
4-2. 外部の力を借りてクオリティを高める
記事の文章やデザインに社内で十分なリソースを割けない場合は、制作会社や外部ライターを活用するのも有効です。
プロの取材力やデザイン力を取り入れることで読みやすくなり、社員も手に取りたくなる社内報になります。
ただしコストはかかるため、社内リソースとのバランスを考える必要がありそうです。
4-3. AIを活用して“時短と効率化”
最近では、AIツールを使って社内報を作成する企業も増えています。
デザインやレイアウトのたたき台を自動で考案したり、原稿の文章作成やリライトを補助したりすることで、担当者の作業負担を大幅に減らせます。
「ゼロからすべて作る」のではなく、「AIが出した案をベースに人が仕上げる」形なら、効率的に質の高い社内報を発行可能です。
限られたリソースで継続する中小企業には特に有効な手段といえます。
4-4. 新しく入社した社員や若手社員に任せるのも一つの方法
新しく入社した社員や若手社員に社内報の担当を任せるのも効果的でしょう。
社内報づくりには以下のような工程が含まれ、学びの機会としても有用です。
- 制作方針の会議での企画立案や意見出し
- 上長や役員への報告・承認のプロセス
- 先輩社員への取材アポやインタビュー
- 外部業者(デザイン・印刷)とのやりとり
- 全社への発信・配布
これらを経験することで、自然と社内外のコミュニケーション力や会社全体の業務理解が深まります。
社内報は情報発信の場であると同時に、人材育成の場としても活用できます。
4-5. 制作体制を決めるポイント
どんな形であっても、社内報は「継続」が大切です。
- 無理のない体制であること
- 会社の規模や目的に合っていること
- 経営層が「社員定着のために必要」と理解していること
完璧な体制を整える必要はなく、自社に合ったやり方で無理なく続けられる仕組みこそが成功のカギになります。
まとめ:社内報は社員定着のための基本ツール
今回の記事では「10月5日=社内報の日」に合わせて、社内報の基本と効果を整理しました。
ポイントを改めて振り返ります。
- 社内報とは?
会社の方針や日々の活動を社員に伝える社内コミュニケーションツール。 - 社内報を出す意味と効果
「聞いてない」のトラブルをなくす、孤立感を減らす、成功事例の共有、採用広報、制度の活用促進など、多面的に社員定着への貢献が期待される。 - 媒体の種類と特徴
紙、PDF、Web、チャットツールなど、自社のIT環境・社員構成・予算に応じて選べる。
ハイブリッド型も有効。 - 制作体制の考え方
中小企業では総務・広報・人事がまとめて担うことが多いが、外部委託やAI活用で負担を減らす方法もある。
また、人材育成目的で新しく入社した社員や若手社員に担当させることも有効。
社内報は、単なる情報発信ではなく、社員が会社を理解し、安心して働き続けるための土台です。
「自社にあったやり方」で始めれば、小さな規模でも十分に効果を発揮できるでしょう。
社内報の他にも定着施策をお探しなら

『定着の樹』では、社内報をはじめとする職場のコミュニケーション改善や、採用から定着につながるヒントを毎月お届けしています。
- 各分野専門家による監修記事
- 採用・定着の工夫 など、経営者や人事担当者に役立つ情報をお届け
- 月1回のメールマガジンで最新記事やイベント情報もお知らせしています。
登録は30秒で完了&完全無料!
▼こちらから、今すぐご登録いただけます。
この記事に付いているタグ




