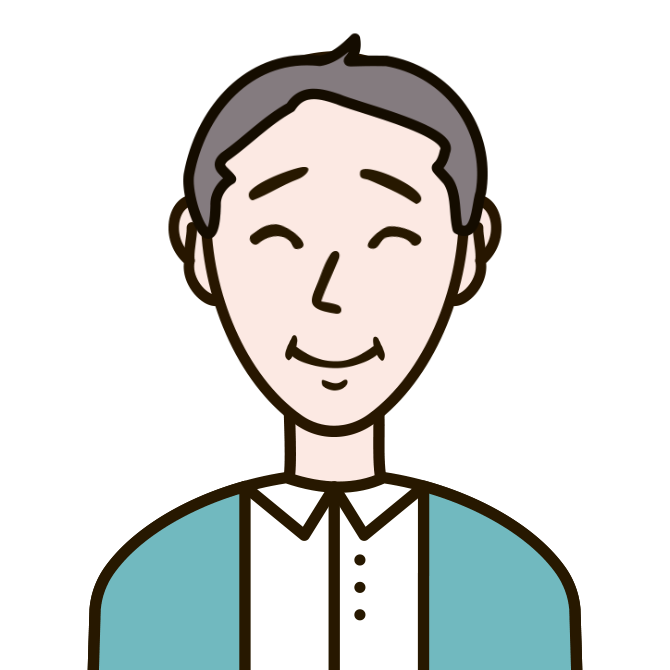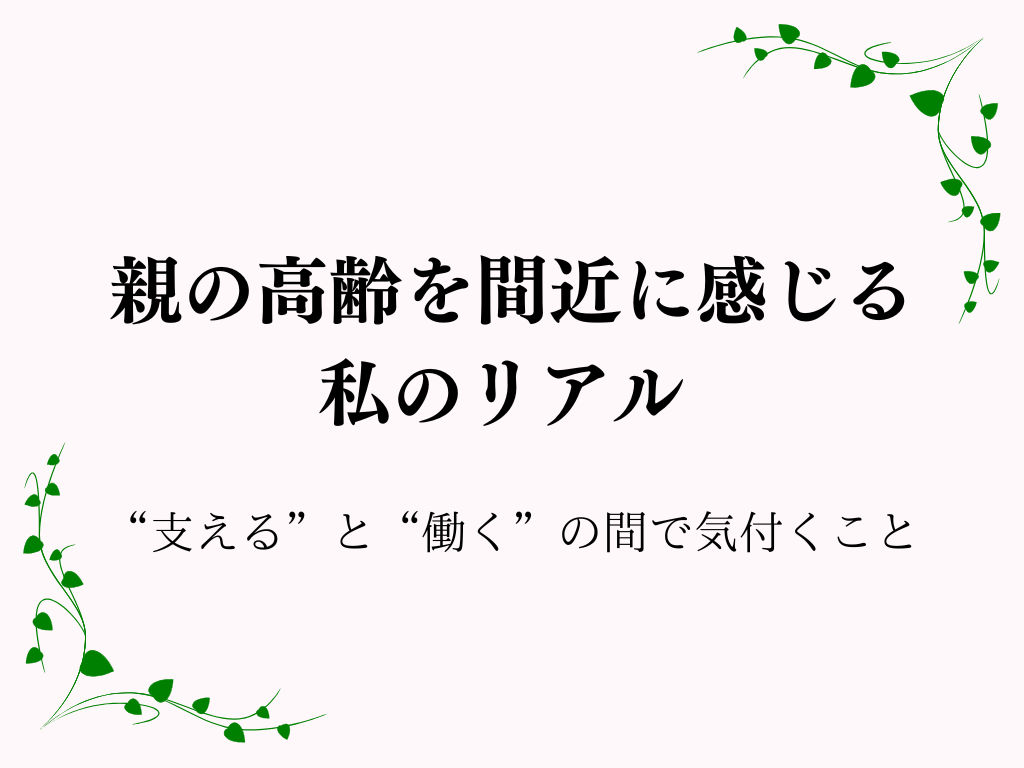
こんにちは。編集部スタッフのNこと名取です。
来週、11月11日は「介護の日」。
今回のスタッフコラムでは、この日にちなみ、私自身の実生活の中で感じている“介護”についてお話ししたいと思います。
正直、「高齢」とは言っても、元気でよく喋る父や母が“要支援”とか“介護”とか、そんな言葉の対象になるとは、今もまだ現実味は薄いように感じます。
しかしながら、私の働き方や暮らしは、「何か」が少しずつ変わりはじめているようにも感じています。
目次
少しずつ、静かに、始まった「支える日々」

私は父母と共に、実家で生活をしています。
両親とも、認知症でもなく、まだ足腰もしっかりしています。
ただ、病院の予約がスマホではうまく取れなくなってきたり、薬の管理が少しあやしくなってきたり……。
そんな“ちょっとした困りごと”が、日常の中にぽつぽつと現れはじめました。
最初は週に1回程度の買い物付き添いだけだったのが、次第に通院送迎、銀行手続き、役所への同行と、“私にしかできない”用事が増えていきました。
誰かに「介護をしてる」と胸を張って言うほどのことではない。
でも、確実に生活の中に“家族を支える時間”が増えていく。
それが、今の私の日常です。
仕事を理由に、心が離れてしまいそうなときもある

私の職場は各々の家庭の事情を汲んでいただける、理解のある職場ですが、もちろん、全て自由に時間を動かせるわけではありません。
親の通院のために午後半休を取ると、翌日は溜まった仕事でてんてこ舞い。
気がつくと、自分が体調を崩してしまいそうになっていることもあります。
何より辛いのは、「ああ、今日も父や母にちゃんと向き合えなかったな」「仕事を理由に逃げてしまったな」と思う瞬間です。
通院の車の中でスマホばかり見てしまったり、早く用事を済ませたくてつい返事が雑になってしまったり……。
そんな自分を責めたくなる気持ちと、「仕方ない」で済ませたい気持ちの間で揺れる日々。
“高齢の両親と共に生きる働き方”は、時間だけでなく、心の余裕も試されるのだと感じています。
「安心する」と言う父に救われた日

ある日、父がこんなことを言いました。
「仕事もあるだろうに。でも、居てくれると安心するよ。」
なんてことのない一言ですが、私はその言葉にものすごく救われました。
“やってあげている”つもりでいた私の中に、“一緒に過ごす時間を大切に思ってくれていた”父の気持ちがあったんだと気付いたからです。
それからは、できるだけ“義務”ではなく“対話”の時間になるように意識するようになりました。
通院の待ち時間にお互いの近況を話したり、昔の写真を見ながら思い出話をしたり。
忙しい中でも、そんな時間が少しずつ増えてきました。
「似て否なる」育児と介護のリアル
職業人として社会と関わる中で、時折「これって育児と同じように考えていいのかな」と思いを馳せるときがあります。
その時々に行き着くのは、育児と介護は「似ているようで、まったく違う」のだという考えです。
親の望む関わり方(意思)、兄弟親戚といった周囲との関係性(環境)、家族との距離感(生き様、価値観)……
あまりにも”個人ごと”過ぎるがゆえに、働く仲間には(仲間にこそ)言い出しにくい気がしています。
そして何より、子育ては“明るい話題”として共有しやすいけれど、介護は“ちょっと重たい話”に思われてしまうことが多い。
職場で言い出しにくいのは、その空気の違いもあるかもしれません。
ひとりで全部、抱え込まなくていい
高齢の家族を支えるといっても、全部を自分でやらなければならないわけではありません。
地域包括支援センターや、訪問看護、家事代行サービス──頼れるところは意外とたくさんあります。
私も、最初は「家族だから自分がやらなきゃ」と思い込んでいましたが、少しずつ人に頼ることで、父母との時間に心の余裕が生まれるようになりました。
結局のところ、自分自身が「元気でいること」が、子の立場としていちばん大切なことだと、今は思っています。
最後に──ゆるやかに、でも確実に訪れるそのときに向けて

父母をはじめ、家族全員、今も元気に過ごしています。
でも、年齢のことを考えれば、「この日常が永遠ではない」とどこかで感じています。
だからこそ、今できることを丁寧に、でも無理せず続けていきたい。
働きながらでも、父母と向き合える時間をつくっていきたい。
“介護”と“仕事”という言葉に捉われ過ぎず、
“家族として”“自分として”できることを、できる範囲で続けていく。
それが今の、私なりの「親の高齢を間近に感じる、子のリアル」です。