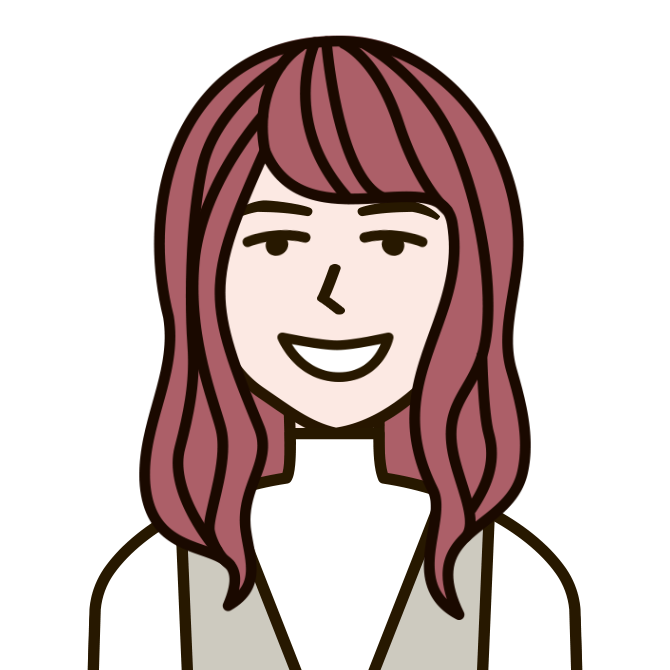東日本大震災から14年が経ちました。
毎年3月11日が来るたびに、「あの日」を振り返る人もいれば、日々の忙しさの中でいつの間にか記憶が薄れつつある人もいるかもしれません。
震災の経験は、働き方や生き方にどのような影響を与えたのか?
あの日、何を感じ、どんな行動をとり、そこから何を学んだのか?
今回は、定着の樹(ヒトベース)のスタッフや専門家の皆さんに、3.11当日の記憶と震災から学んだことをお聞きしました。
目次
3.11 あの日、どこで何をしていたのか?
あの瞬間、人々はそれぞれの場所で、思いもしない状況に直面しました。
💬 加藤 雅子さん(Kキャリアウィング)

さん
ホテルでランチをして帰るところだったので、被災直後はホテルの駐車場で待機しました。
💬 匿名希望さん
仙台市内の職場で被災。徒歩で帰宅後も部屋にいることが怖く、友人の車で一夜を過ごした後、被害の少なかった実家(県北)へ避難しました。
💬 高橋 直樹さん(自走型組織づくりコーチ)

さん
(前職のときでしたが)訪問医療マッサージのサービス中で、マッサージ師の先生と利用者様のご自宅にいました。
💬 鈴木 慎太郎さん(浜通り社会保険労務士法人)

休日で海の近くにいました。被災後、両親の安否が心配で仙台の自宅から南相馬の実家に向かいました。南相馬の実家に向かう途中、国立宮城病院で一夜を明かしましたが、病院内は戦場だったことを今でも鮮明に覚えています。
💬 渡辺 徹(定着の樹・ヒトベース株式会社)

仙台駅前のホテル一室で説明会(就職支援の仕事で未就職者の対応)をしていました。揺れがすごく、外に出ると腰を抜かして立っていられない人がたくさんいました。JALシティのスタッフの方が下で避難している方々に毛布や布団を持ってきて配っていた姿が印象に残っています。
💬 はっしー(定着の樹・ヒトベース株式会社)

当時中学1年生。先輩の卒業式が終わり、帰宅した直後に被災しました。両親ともに仕事に出ていたので、団地内に住む人たちみんなで広場に集まって待機しました。
14年経った今でも、「あの日、どこにいたのか」「どんな状況だったのか」 を鮮明に覚えている人は多いはず。
それだけ、自然災害が人生に与えた影響は大きいものでした。
震災が「働き方」に与えた影響とは?
あの日を経験したことで、働くことへの考え方が変わったという人も多くいました。
「日頃からの備えと安全意識」

さん
万が一に備え、業務開始前に安全行動の基本をリマインドする習慣がつきました。
長年キャビンアテンダントとしてご活躍されていた加藤さん。
安全管理の経験が豊富であっても、「まさか」という瞬間は、いつ訪れるかわからない上、訓練通りの事象は発生しないのが自然災害の恐ろしさ。
ご自身や周りの安全を守るために、日々の習慣の中に防災の意識を取り入れることが大切ですね。
「大切なものを見直すきっかけに」
震災を経て、大切な人や大切にしたいことが明確になりました。震災翌月には、それまでの仕事をすべてリセット。震災復興の仕事に携わった後、結婚して家庭を築くことを決断しました。
震災後、これまでの働き方や人生を見つめ直し、新たなキャリアや家庭の選択をした人もいるようです。
「仕事」だけでなく、「生き方」そのものを見直すきっかけになった人も少なくないのではないでしょうか。
「自立と協力のバランス」

さん
できること・できないことを整理し、社員教育にも取り入れました。もし1人になっても行動できるように。
「誰かが助けてくれる」と思うのではなく、それぞれが自分の判断で動けるような仕組みをつくること が、これからの組織には求められるのかもしれません。
「震災がキャリアを変えた」

福島県の浜通り地方が原子力発電所事故により被災。社会保険労務士の資格取得後、復興に寄与したいという想いから故郷に戻り起業を決意しました。震災が私の人生を大きく変化させたと実感しています。
震災をきっかけに、「自分にできることは何か?」を考え、行動に移した人もいます。
鈴木さんはその一人で、地元で2013年に「浜通り社会保険労務士事務所」を開設。
「困難の中でも、自分ができることを模索し、行動を起こすこと」—その姿勢が、新たなキャリアの道を開く力になったのかもしれません。
「有事のときこそ、人とのつながりが重要」

あの日、就職支援説明会に来た方はその後どうやって帰ったのか?知ることはできませんが未だに気になっていることです。有事の時に「自分の足で歩く力」「仲間を作ること」がいかに大事か、ということを教えてくれた気がします。
災害時には「個人の力」と「人とのつながり」、どちらも欠かせません。
助けを求められる関係性を築くこと、そして自ら動ける力を養うこと—そのバランスが、これからの働き方にも求められるのではないでしょうか。
「震災の記憶が風化していく中で、考え続けることの大切さ」

宮城では震災に関する報道が続いていますが、首都圏では3月11日が近づかないと話題に上がる機会が少ないように感じます。 これは、昨年の能登半島地震や2016年の熊本地震、さらに遡れば阪神淡路大震災についても同様で、時間が経つにつれ、全国的に報じられる機会が減っていくことを実感します。
しかし、災害の記憶が薄れていくことは避けられない一方で、「何を大切にしたいのか」「どんな備えが必要か」を考え続けることはできるのではないでしょうか。 だからこそ、この記事を通じて、読者の皆さんにも “失いたくないもの・守りたいもの” を改めて考える機会になればと思いました。
震災の記憶は、地域によって風化のスピードに差があるかもしれません。
しかし、大切なのは 「あの経験を忘れないこと」だけではなく、どんな状況でも『自分にとって本当に大切なものは何か?』を考え続けること。 それこそが、14年経った今だからこそ、より意味を持つのではないでしょうか。
おわりに:3月11日を「未来につなげる日」に
東日本大震災から14年。時間の経過とともに、3.11について語る機会が少しずつ減っているのも事実です。
しかし、あの日を振り返ることは、単なる記憶の風化を防ぐためだけではなく、「これからどう生きるか」を考えるための大切な機会なのではないでしょうか。
この記事を読んでくださった皆さんにも、「自分にとって本当に大切なものは何か?」を改めて考えるきっかけにしていただけたら と思います。
3月11日を、過去を振り返ることで未来を考える日に。
一人ひとりが「大切なもの」を見つめ直し、それを次の世代へつないでいけることを願っています。