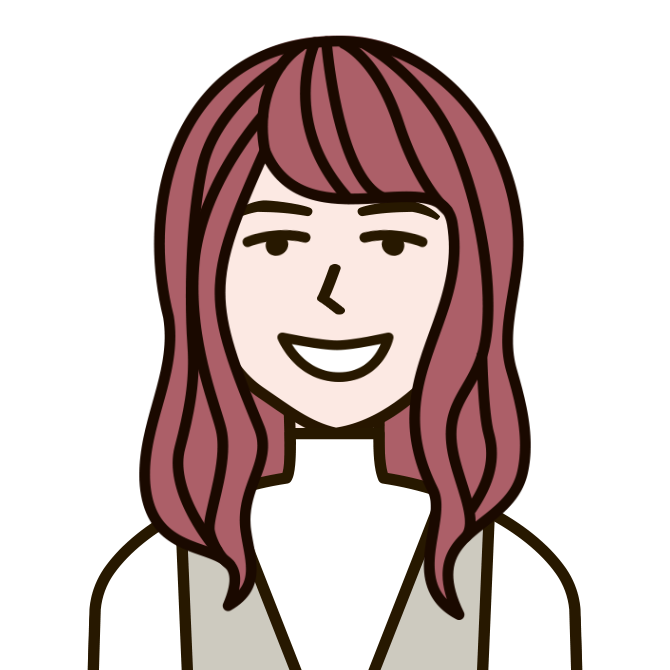こんにちは、編集部のはっしーです。
先日SNSで「今日、9月19日は『育休を考える日』です!」という投稿を目にしました。
気になって調べてみると、この記念日は積水ハウスが2019年に制定したもので、
男性の育児休業取得を社会全体で考えるきっかけにしてほしい、という思いが込められているそうです。
ちょうど友人と「男性×育休」について話したことを思い出したので、
今回は私自身も「人材の定着」という観点からも改めて考えてみたいと思います。
目次
1. 男性の育休って本当にとれるの?
1-1. 生の声を聞いてみた
ついこの前、友達と集まったときに「男性の育休って本当にとれるの?」という話題になりました。
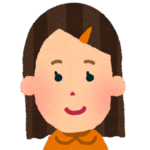
私の兄夫婦のところは5年前に子どもが生まれたんだけど、
そのときに兄は1か月まるまる育休取ったんだって。
赤ちゃんって24時間体制で見ないといけないし、
ママ(兄の妻)も産後すぐで体力が万全じゃないからって、家事も含めて頑張ったみたい。
1か月間、生まれたての可愛い我が子のそばにいて、
その後会社に復帰したら「早く子どもに会いたいから仕事を早く片づけなきゃ!」って意気込んでて、むしろモチベーションになってるらしいよ(笑)

今でこそ「産後パパ育休」っていう制度があるみたいだけど、
その前からパパが1か月まるまる育休取れるっていい会社だね!
復帰後も我が子をモチベに仕事頑張れるって理想だ~

私の友達も最近子どもが生まれたんだけど、
その旦那さんは収入のことを気にして友達と話し合って育休は取らなかったの。
でも在宅勤務の日数を増やしてもらえたらしいよ。
しかも旦那さんの上司が
「連絡が取れて仕事が回れば、多少子どもの世話で席を外しても構わない」
って言ってくれたんだって!
こういう会社や上司がもっと増えるといいよね~

そんな優しい会社あるの!?
でもこういうのって、その人と会社の間に信頼関係があるからこそ成り立つのかもね。
多少ルールを厳しくせずともやっていける環境って羨ましい!
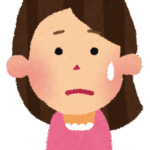
逆にうちの夫は仕事柄、夜勤や休日出勤もしないといけない職場だったし、
会社からも「男性が育休取った前例はないから…」って言われたみたいで…。
仕方ないから、産前産後の数か月は私や夫の実家を頼りながらどうにかしたの。
でも結局、夫が「これじゃ家庭と両立できないね」ってなって
もう少し子育てに時間をとれる職場に転職しよう、って決めたところだった。

そっかあ、C子の所はそんな大変なことになってたんだね💦
やっぱり会社が変わらなきゃ自分が変わるしかない…
つまり自分の環境を変えるしかないってことだよね~
3人の話を聞いて、やっぱり今でも会社によってパパの育休に対するスタンスは大きく違うんだなあと実感しました。
1-2. 法律があっても、実際に申し出にくい現実
で、この記事タイトルの「男性の育児休業は本当に取れる?」という問いについては、
結論、法律上は「男性だから育休が取れない」ということはありません。
育児・介護休業法で、従業員から申出があった場合には会社は原則として拒めないと定められています。
さらに2022年の法改正では、企業に対して育児休業制度の周知や、社員への「取得意向の確認」を行うことが義務付けられました。
会社として制度を知らせ、選択肢を提示することは、非常に重要なこと。
しかし実際には、収入面の懸念や「周りの目を気にして遠慮してしまう」「自分だけ抜けて迷惑をかけるのでは」といった心理的な壁が根強く残っているのも事実としてあるようです。
加えて、会社は自社の利益を追求する場でもあります。
「育休制度を整えるのは理想だけれど、現場の人手やコストの余裕がない」と悩む経営者も多いでしょう。
つまり「法制度としての仕組み」と「職場での本当の取りやすさ」の間には、まだ大きな隔たりがある。
これこそが、日本社会に残された課題だと私は感じます。
同じ「子どもが生まれた」という状況でも、
- A子のお兄さんのように1か月の育休をしっかり取れる職場
- B子の友達の旦那さんのように育休は難しくても在宅勤務など代替策を工夫してくれる職場
- C子の旦那さんのように、育休をとるのはおろか長時間労働が慢性化していて、転職という選択肢を迫られる職場
…と、会社のスタンス次第で社員や家族の経験はまったく違ってきます。
2. 制度を「使える状態」にすることが定着のカギ
企業が子育て世代の社員に向き合うときに重要なのは、制度を「ある」状態にするだけでなく、
安心して申し出られる雰囲気=心理的安全性をつくることではないでしょうか。
「制度はあるのに誰も使えない」状況は、社員にとって大きな不安要因となり、
ライフステージが変化したタイミングで離職につながるリスクにもなりかねません。
一方で、育休に限らず、在宅勤務や勤務時間の調整など、業務の取り組み方を工夫できる会社は、
社員にとって安心感につながり、採用力や定着率の向上に結びつくことも少なくありません。
- 家庭責任を分かち合うことで、女性がキャリアを中断せずに働き続けられる可能性を高め、
社会的意義を担うと同時に会社のイメージアップにもつながる - 若手世代にとって「長く働ける会社」という安心感になる
- 結果として、採用力や定着率の向上に寄与する
育休をはじめとした様々な制度を「コスト」ではなく「投資」として捉え、心理的にも文化的にも取りやすい環境を整えられるかどうかが、
これからの企業成長の分かれ道になるのではないでしょうか。
3. さいごに
男性の育児休業をめぐっては、法律や制度の整備が進んできたとはいえ、「本当に取りやすい」とまでは言い切れないのが現実です。
だからこそ、企業と従業員が「どうすれば働き続けられるか」という視点を共有し、少しずつ文化をつくっていくことが欠かせません。
また、育休は“キャリアの中断”ではなく、“キャリアを強くする期間”にもなり得ます。
休業期間をとおして家族と向き合い、自分のキャリアを見直し、会社や同僚との信頼を深めるきっかけにもなるからです。
「育休を考える日」をきっかけに、読んでくださった方が、
「もし自分が育休を取るとしたら?」
「もし自分の職場で部下が育休を申し出たら?」
など、それぞれの立場で思いをめぐらせるきっかけになれば幸いです。
その小さな一歩が、働き続けられる会社づくり、そして人材の定着へとつながっていくはずです。
子育て世代の社員も安心して働ける職場づくりを考えるなら

家庭を持つ若手・中堅社員が長く安心して働ける環境にするためには、様々なアプローチが必要になります。
定着の樹では、そんな“従業員が定着し、一人ひとりが戦略化していく職場づくり”に役立つヒントを配信中!
- 各分野専門家による監修記事
- 採用・定着の工夫 など、経営者や人事担当者に役立つ情報をお届け
- 月1回のメールマガジンで最新記事やイベント情報もお知らせしています。
登録は30秒で完了&完全無料!
▼こちらから、今すぐご登録いただけます。
この記事に付いているタグ